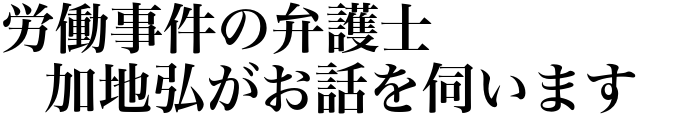労働審判、加地弘の感想
労働事件の弁護士として、労働審判を数多く経験してきました。
思うところを述べていきます。
30秒でわかる、労働審判制度の概要
まずは一応、制度の概要からさらっと説明します。
既に知っている方も多いでしょう。そういう方はどうぞ読み飛ばしてください。
【労働審判とはどんな制度か】
- 労働事件に特化した小型の裁判
- 2006年に始まった制度で、すぐに人気となった
- 原則1〜3回の審理で終わるので、1〜3ヶ月でのスピード解決を期待できる
- 非公開の手続きであり、外部(例えば報道機関)に知られることがない
【労働審判の短所】
- 3回の審理で終わらないような複雑な事件では利用できない
-
会社・事業主を相手に申し立てることしかできない
(例えばセクハラした本人を対象にするのは無理) - 受け取れるお金は訴訟して勝ったときより低額になりやすい
なぜ労働審判は早いのか
なぜ審理を早く終えられるのか、それは労働審判が口頭主義を採用しているから、です。
通常の訴訟では、相手方とのやり取りは文通のように書面で行われますが、労働審判では、関係者が一堂に会し、口頭で自分の主張を伝え、相手の主張にも口頭で反論をします。
文通より口で伝えたほうが早いに決まっているわけで、それがスピード解決を果たせる理由です。
しかし反面、その場で相手への反論をしなければいけないのですから、難しさは上がってしまいます。
労働審判の現実(加地弘の感想)
ここからは労働審判の現実について述べていきたいと思います。
現実といっても私の主観が多くなるのであるいは極論かもしれませんが、一般論ばかり載せても面白くありませんし、参考にはなると思います。
労働審判を選ぶ人はけっこう多いんですか?
多いです。この制度は開始当初から人気が出ました。統計によれば労働事件において、通常の訴訟の数と労働審判の数は大体同じぐらいです。
しかも、数が同じぐらいといっても、労働審判が決裂した後に訴訟に移行したケースもあるでしょうから、近頃では労働事件を裁判に訴える際、労働審判こそが最初の選択肢になっている、といっても良さそうです。
なぜそんなに人気が出たんですか?
やはり、早ければ1ヶ月、長くても3ヶ月程度で終わるというスピード感こそが最大の魅力です。そのうえ解決水準もまずまず、と考える弁護士が多いのでしょう。
とはいえ私はあまり選ばなくなりました。
なぜ選ばないんですか?
解決水準・・要するに受け取れる金額・・に満足できないことが多いからです。
ケースバイケースではありますが、概して言えば・・
の順で、獲得金額が増えます。
そこで多くの事件において私はまず交渉による解決を目指し、交渉がまとまらなければ訴訟を選ぶことになります。
交渉でまとまる可能性があるのに労働審判を選ぶ意味はあまりないと感じますし、かといって交渉でまとまらなかった事件を労働審判に持ち込んでも決裂する可能性が高そうですから、積極的に選ぶ理由を見出し難いのです。
じゃあ加地さんは労働審判の経験があまりないんですか?
いいえ、以前はかなりやっていましたし、今でも他の人に比べて少ないわけではないと思います。 労働審判が向いているケースもあるので。
労働審判を選ぶ弁護士が多いのは、そのほうが弁護士にとって手間がかからず楽だから、ではないんですか?
たしかにトータルで見れば、短期間で済む労働審判を選ぶほうが、訴訟をした場合より弁護士の手間が減ります。
そのかわり労働審判においては、初回に全てを賭けなければならず、訴訟であれば後日に回せたはずの作業も、前倒しでかなり急いで進めなければいけません。抜かりは許されません。
弁護士は他の案件も抱えていますから、1つの案件に短期集中で取り組まされるのは、あまり嬉しいものではありません。そのため、労働審判が訴訟より手間が少なく楽だ、とは私はまったく感じません。手間という点ではむしろ大変だと感じます。
相手方の弁護士の仕事を見ていても、どちらかといえば、むしろ訴訟より労働審判のときのほうが頑張っている(良い仕事をしている)印象を受けます。
大変なのに多くの弁護士が労働審判を選ぶというんですか?本当にそうなのかなぁ・・。
労働審判は、解決水準はともかくとしてまとまる可能性が高く、はっきり負けることは少ないイメージがあります。訴訟ではっきり白黒つけられるのを恐れる弁護士は、労働審判を選びやすいところが、もしかしたらあるかもしれません。
それと、この仕事をしていて感じるのですが、弁護士の中には、相手方と連絡を取り交渉することを嫌がる人が、どうも少なからずいます。
というのも相手方(会社)にとって、金銭などを要求してくるこちらからの連絡はぜんぜん嬉しくないものです。繊細な性格だとそういう連絡を相手方に直接することに気が進まないのではないでしょうか。
あるいは、弁護士の交渉というのは、相手方と激しく対立しながら同時に協調する、という相反することを求められるものですが、そうしたどっちつかずの状態に居心地の悪さを覚える人もいそうです。
そういう弁護士にとっては、交渉をせずにいきなり労働審判を申し立てる方が、裁判所が間に入ってくれるぶん、気が楽なのかもしれません。
労働審判を選ぶと弁護士費用は安くなるんですか?
弁護士費用は事務所ごとに違うでしょうが、うちの事務所では、労働審判にかかる費用は通常の訴訟の場合と同じです。
争い方ではなく、あくまで会社への請求金額と、依頼人の獲得金額、事案の複雑さなどを元にして、弁護士費用を決めています。
ただし先述のように、労働審判では獲得金額が全体的に低く抑えられる傾向があるので、結果的には弁護士費用も下がることが多い、とはいえるかもしれません。
なぜ労働審判だと獲得金額が抑えられやすいのですか?
第1回目の審理でほとんど決着がついてしまうのが労働審判です。
通常の訴訟や交渉であれはお互いの主張する金額の隔たりをじりじり埋めていく時間がありますが、それがないのでザックリとした解決になってしまいがちです。
そのうえ労働審判は、争いを話し合いでまとめることに力点を置いているところがあります。 審判官らは「裁定者」というより「仲裁者」になろうとしている・・そういう印象を通常の訴訟に比べると受けます。
円満にまとまらなかった場合は審判(←判決のようなもの)が出るわけですが、仲裁者としてはせっかく自分が間に入って取りなすのであれば、できればまとまってほしいと考えるのではないでしょうか。
となると審判官らが出してくる調停案(←和解案)は、双方が受け入れやすいであろう内容になりがちなわけで、得てしてそれは、お互いの主張を「足して2で割った」ようなものになります。
事件の種類にもよるのですが、それではなかなか、満足のいく解決水準に達しないのです。
じゃあ調停案を蹴って審判をもらえばいいんじゃないですか?
仮に審判官らが出してくる調停案(←和解案)を拒否して審判(←判決)をもらったとしても、その審判の内容は、けっきょく調停案とあまり変わらないことが多いです。↓
会社は労働者に100万円を支払いなさい。
↑このような調子です。
金額を上げようとして調停を拒否してもあまり意味がない・・つまり裁判所から出される最終的な調停案は、実質的には裁判所からの命令と同じようなものなのです。
そうした調停案に満足できず、通常の訴訟に移行する可能性が高そうなのであれば、最初から訴訟をすれば良かったと私は思ってしまいます。
加地さんはどういうケースで労働審判を選ぶんですか?
まず、請求額が少ないケースです。それなら訴訟をしたときと獲得金額に大きな差が出ないと思われるからです。
たとえ請求額が多くても、退職金請求や未払い残業代請求のように、請求額の根拠がかなり明確な事案であれば、労働審判で問題ないでしょう。そう大きく譲歩させられることはなさそうだからです。
こちらの持っている証拠が弱いとき、は、労働審判が特に向いていそうです。
というのも先述のように、労働審判は口頭主義です。当事者が自分の口で語ることが中心となります。
こちらに固い証拠はないけれど会社が嘘をついているのは確か、というケースでは、相手方に喋らせれば色々ボロを出してくれそうです。
あとは単に、依頼者本人が労働審判を希望した場合、です。
早く終わるなら会社と闘ってみてもいい、という人もいるので。
向いている事件、向いていない事件
労働審判に向いている事件、向いていない事件、私の経験から述べてみます。
1. 不当解雇
労働審判といえば不当解雇、というイメージですが、私はあまり選びません。 受け取れる金額に納得がいかないことが多いです。
労働審判は1〜3ヶ月という短期で終わるわけですが、それゆえ労働審判をしているとき、労働者はふつう、解雇されてからまだ時間がそう経っていません。数ヶ月ぐらいかもしれません。
そのためなのか、労働者の受けた損害が軽く見積もられがちであると感じます。 バックペイ(解雇されてからこれまでの期間の賃金)が、低く考慮されてしまいやすいので。
私としては、通常の訴訟をして勝てばもらえたであろうバックペイ1〜1年半分を基準に、解決金を算出すべきと考えるのですが・・・。
ちなみに労働審判を選ぶと、
と裁判所からみなされると思います。
あくまで復職にこだわるなら、別の手段を選びましょう。
2. 退職金請求
争点はそう複雑にならないことが多いでしょうから、労働審判で対応可能と思われます。
退職金は請求額が大きくなる可能性があり、その点であまり向いていないと思うかもしれませんが、退職金はその金額が規程で明確に定められているものです。
金額の根拠が明確な請求は、労働審判をしても「足して2で割られる」ことがありません。 例えば1000万円を請求したのに500万円で譲歩させられる、といったことはないでしょう。
3. 未払い残業代請求
労働審判制度が始まる前、残業代請求はこの制度に不向きだろうと言われていました。
というのも、残業代事件では残業時間を1分単位で争うことになります。 そうした細部にこだわる必要のある争いを、わずか3回の審理で終えられるとは思われていなかったのです。
ところが制度が始まってみると、意外にも残業代請求は労働審判向きでした。 以下のような理由からです。
通常の訴訟においては、裁判官は原則として、残業時間を1分単位で正確に認定しなければいけません。 1分でも計算を間違うと上で判決がひっくり返るので、裁判官も大変です。
しかし労働審判では・・↓
といった調子で、大雑把な審判(←判決)を、審判官が出すことができます。 とても柔軟な制度なのです。
そして、どうせこうした大雑把な審判が出るのであれば、労働者側も会社側も、1分単位で残業時間を細かく争う必要を、あまり感じなくなります。ザックリとした争いに落とし込めるので、3回の審理でも大丈夫だったのです。
私はむしろ、残業代請求事件は労働審判のほうが向いているかもしれないと思います。
とはいえ、労働者が管理監督者に当たるのか、といった争いでは、妥協的な解決をはかりにくく対立が先鋭化します。 そうしたケースには不向きでしょう。
5. パワハラ セクハラ
ハラスメント事件においては、確たる証拠に乏しく、当事者の証言が重要になるケースが多くなります。そのため、当事者が直接自分の口で語ることになる労働審判は向いていると思います。
とはいえ、ハラスメントをした本人を相手にすることはできません。 あくまで会社を相手に申し立てることしかできないので、加害者への処罰感情の強い人は、労働審判を選ばないかもしれません。
なお、労働審判は非公開の手続きなので、こちらが申し立てた(訴えた)こと、会社が申し立てられた(訴えられた)こと、が基本的には外部(例えば報道機関)に漏れることがありません。
それを好ましいと考える人もいれば、むしろ訴えたことを、懲罰の意味で、世間に知らしめたいから通常の訴訟のほうがいい、と考える人もいます。
6. 労災事件
労基署から労災が認められず、その決定に不服で国を訴える、というケースでは、そもそも労働審判を選べません。 申し立てる相手は会社や事業主に限られるからです。
一方で、労災について会社にも責任があったのだから損害賠償を請求する、といったケースでは、労働審判を選ぶことが一応は可能です。
とはいえ普通は選びません。会社の安全配慮義務違反を問う争いは、具体的に何が会社の安全配慮義務なのかをまず明確にせねばならない、などの理由で、複雑になりやすいからです。
7. 競業避止義務事件
争点が多岐にわたるので全く向いていません。
そもそも会社のほうから労働者を訴えてくることがほとんどなので、労働審判が向いているかどうか、こちらが検討する意味があまりなさそうです。
次のページでは、労働審判当日の様子・闘い方について述べます。 当日何を聞かれるのか不安な方はぜひご覧ください。
【次のページ】 » 当日の闘い方・心構え