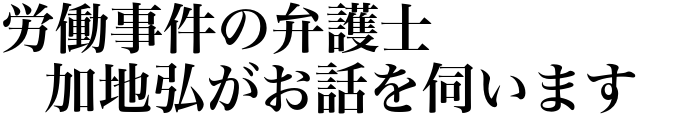不当解雇かもしれないと思ったら
まずは基本的なところから始めましょう。
解雇は簡単にはできません。
ただ要らないからという理由で、会社は労働者をお払い箱にはできません。日本の法律ではそうなっています。
ちょうど結婚を考えてみると良いでしょう。雇用契約は会社と労働者の結婚といえます。 一度結婚をしたら相手のことが嫌いになったからといって、簡単に別れられるものではありません。
どうしても離婚するなら、相手に慰謝料を支払う覚悟がいるはずです。支払う覚悟があっても向こうが受け取ろうとしない(離婚に同意しない)可能性さえあります。
労働者と会社の関係もこれに近いものがあり、一度結んだ契約を会社の方から簡単に解消することはできないのです。
労働者はもちろん、使用者の中にもこのことを知らない人がいます。
例えば以下のような主張は誤りです。↓
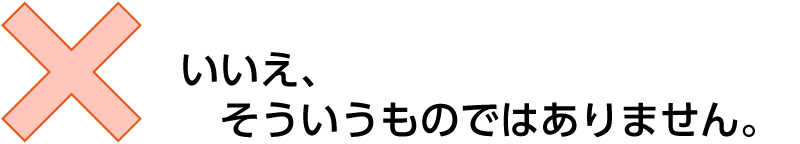
民間企業の社員だったら、いつ解雇されても文句が言えないことの裏返しでしょ?
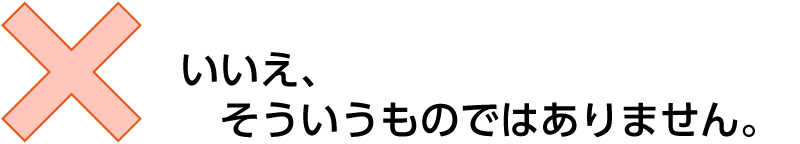
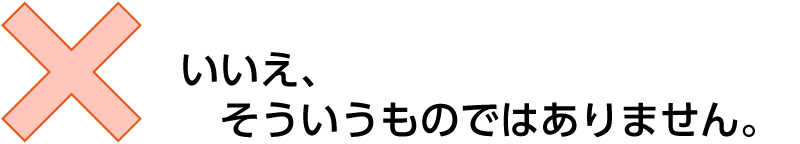
労働者の中にも次のように考える人がいます。↓
特に最近の若い人は不景気の時代しか知らないので、ちょっとこちらが驚いてしまうほど人が好いというか、権利意識の低い人が多いです。
労働者の方でこうした考えを持つのは自由であり、あるいは讃えられるべきなのかもしれませんが、今は法律の話をしましょう。 こういう考えを経営者が押し付けることはできません。法は労働者を保護する立場を取っています。
- 嫌いだから
- 労働者が妊娠したから
- 労働者が労働組合に加入しているから
↑例えばこうした理由での解雇は論外であり、決して認められません。
ここまでデタラメな理由による解雇は、さすがに大きな会社ではなかなか見られません。しかしワンマン社長率いる中小企業では、まだ多く見られるようです。
一般に思われているほど、解雇される労働者は多くありません。
多くの人は肩叩きを受けると、泣く泣く自分から退職する道を選ぶからです。
これは合意に基づいた退職と呼ぶべきもので、解雇とは法律上異なるのですが、そこを混同する人が多いので、クビにするのは簡単という誤解が広まりやすいのでしょう。
本当に合意のうえだったのか、半ば強制だったのかについては、疑問の余地がありますが。
不当ではないとされるとき
解雇が認められる理由は、大きく次の3つです。
1.労働者に重大な規律違反があった
労働者が遅刻や無断欠勤を繰り返した、業務命令に従わないなど勤務態度が悪かった、横領などの重大事件を起こした、というケースです。
非常に悪質だったり、何度繰り返しても反省が無い、などの事情が必要です。 認められるためのハードルは、普通の人が考えるであろう基準より高いといっていいでしょう。
2.労働者の能力に著しく問題がある
「著しく」というのがポイントで、単に他の社員に比べて能力が低かったとか、期待したほどの能力ではなかったという程度の理由では、基本的に認められません。
仮に労働者の能力に相当の問題があるのだとしても、次に会社はその人の能力に今後改善の見込みが無さそうなことまで、併せて証明しなくてはなりません。
これは非常に高いハードルです。何でもそうですが、可能性が無いことを証明することは、その逆よりもはるかに大きな困難を伴うものです。
これから経験を積ませても、研修をしても、部署を変えても、それでも会社にその人の居場所がなさそうなこと、 自信を持ってそう言える根拠を会社は示すことができるでしょうか? 会社にとり難しい裁判になることは想像できるでしょう。
3.会社の経営状態が著しく悪い
会社の経営上の理由による解雇を「整理解雇」といいます。
労働者に特に責任が無いにもかかわらずクビを言い渡す点、が大きな特徴です。当然簡単に認められるものではありません。
経営が著しく苦しいだけでなく、解雇を避けるために経営陣が相当の努力をしたことが証明されないと、認められないことが多いです。例えば新卒の募集を停止する、希望退職を募る、役員報酬を削る、事業再生計画を策定する、等々。
そして整理解雇は会社の経営を建て直すために行われるものなので、通常、解雇を通告される者はそれなりに多くいなければおかしいはずです。
もしも会社が1人2人にしか言い渡していないのであれば、その少額の人件費を削ることが、会社の経営改善にどうしてそこまで重要なのか、合理的な説明をするのが却って難しくなるでしょう。
さりとて大規模の首切りを裁判所が簡単に認めるわけがないのも明らかですから、ハードルの高さがわかると思います。
不当解雇を訴えるとどうなるの?
会社を訴えるには、大きく2つの道があります。
1.自分がまだ従業員の地位にあると主張する
オーソドックスなやり方です。
これが認められれば解雇が無効になるのに加え、それまでの賃金を受け取ることができます。つまり裁判の決着までに2年かかったのであれば、2年分の賃金をもらえるということです。
素直に考えれば、裁判に勝てば労働者は会社に戻ることになりそうですが、現実には会社は労働者に戻ってきてほしくないので、改めて両者が協議し、復職を放棄するかわりに会社が追加の金銭を支払うことで決着する、というパターンが多いです。
もっともそれは裁判を最後まで闘い、解雇無効の判決をもらった場合の話であり、 現実には判決をもらう前に、労働者と会社が復職放棄を前提に、金銭で和解するケースが多いです。
和解をすれば、一般的には、判決をもらった場合に比べ、獲得できる金銭は少なくなってしまいます。
2.金銭による補償を求めること
会社を訴えるもう1つの道は、労働者が退職はするが、会社の不法行為に対する慰謝料などを請求する、というものです。
離婚裁判に例えるなら、離婚はするけれど慰謝料は請求します、ということになるでしょう。
金銭を請求するという点では結局「1」と変わりません。 しかし請求する名目が「これまでの賃金」なのか、それとも「慰謝料」であるかの違いがあります。
これは決して形式的な違いではありません。
慰謝料という形での請求は、「1」のケースに比べ、認められる金額が低く抑えられる傾向があるからです。
つまり労働者に不利なので通常こちらの手段は取らないのですが、労働者が前よりだいぶ良い待遇で既に再就職しているなど、解雇無効を訴えるのがいかにもふさわしくない場合には、こちらを選ぶことになります。
まず、アルバイトや派遣労働での再就職の場合、問題はないでしょう。
ただし元の会社に請求する賃金から、アルバイトで得た賃金の一部が引かれます。
一方で正社員として再就職したケースとなると、なかなか微妙な問題が生じます。 再就職したタイミングで元の会社に戻る意思を放棄した、とみなされる可能性があります。
しかし、私はそういう場合でも構わず訴えています。
再就職した会社を辞めることもできる以上、「再就職=元の会社に戻る意思がない」ではないはずだからです。 事実、これまでこの点(再就職)がネックになったことは、私の経験ではありません。
ただし、もしもあなたが前の会社よりもかなり良い待遇で再就職している場合だと、さすがに元の会社に戻るつもりがなさそうだ、と裁判所が判断する可能性があります。
そのように判断されたケースでは、受け取れる賃金は、それまでの(再就職までの)期間分に限られることになるでしょう。
解雇とお金の問題については、『不当解雇とお金〜その誤解』でもう少し詳しく説明しています。
裁判に勝ったときに返還すればいいだけなので基本的に問題ありません。 勝てばそれまでの賃金をバックペイとして受け取れるのですから、返還するお金に困ることもないはずです。
そう会社は言ってくるかもしれませんが、関係ありません。
ただし解雇されてから会社にアクションを起こさずおとなしくしていた期間が長いようだと、
と判断されてしまうかもしれません。長いこと会社にアクションを起こさなかったのは何故なのか、例えば病気で療養していた等の理由があると望ましいです。
なお、これから失業保険を受けるのであれば、仮給付という形で申請しておくのがいいでしょう。 まさに、裁判で不当解雇を争っている人に、給付されるお金です。
本給付と何が違うかといえば、仮給付であれば失業保険を受け取っていても、求職活動をするようハローワークから言われないのです。
できないことはありませんし、私の事案で復職をはたしたケースも過去にあります。
しかし、自分たちを訴えた労働者を気持ちよく復職させる会社は多くありません。
実際に多いパターンとしては、解雇無効の判決をもらった後、労働者と会社が改めて交渉のテーブルに着き、労働者が復職を諦めるのと引き替えに、会社が追加の金銭を支払うことで決着する、というものです。
あくまで復職を迫ったとしたら、会社はどのような対応をしてくるでしょうか。 会社が何が何でも復職を認めたくないのであれば、会社は高裁に上訴するかもしれません。たとえ勝ち目が無いと彼らがわかっていても。
一種の嫌がらせとして上訴し、あなたが疲れ、和解に応じるのを待つ作戦です。 決着までに数年かかってしまうでしょうから、精神的にも、そして経済的にもあなたは疲弊します。
仮に最後まで闘い抜いて解雇無効の判決をもらったとして、そこでようやく一件落着かといえば、そうとも限りません。頑として復職を認めずに、机を用意しない、閑職を与えるなどの嫌がらせ行為を続ける会社もあるようです。
会社がそんなことをすればまた労働者は訴えるかもしれませんが、そこは会社と労働者の我慢比べです。互いを傷つけ合う消耗戦が、さらに続くということです。
もちろん会社の中には、復職を比較的すんなり認めるところもあるでしょう。 特に大きな企業の場合、労働者と経営陣との間に距離があるので、会社も労働者を戻しやすいし、労働者も戻りやすいです。大規模なリストラにより同じ立場の仲間がたくさんいる場合もそうです。
しかし基本的には、復職を求めるのであれば、訴訟を起こすのは最後の手段にして、 弁護士に示談交渉を依頼したり、労働組合の力を借りるなどして、できるだけ交渉で臨むのが得策と思われます。
不当解雇事件の時効
従業員としての地位確認請求をするにあたって時効はありません。解雇されて20年30年経っていても、ともかく理屈のうえでは、会社を訴えることができます。
ただし請求できる金額(その計算期間)は制限を受けます。 裁判を起こした時点で請求できる未払い賃金(バックペイ)は、過去3年分までに限られます。
とはいえその3年という期間も、いちど裁判が始まってしまえば関係ありません。 裁判が終わるまでに5年かかったのであれば5年分のバックペイを受け取れます。あくまで裁判を起こした時点で請求できるのが過去3年分までということです。
その3年という時効も、内容証明を会社に送ることで1回だけ(半年間)延ばすことができるのですが。
加地弘と不当解雇事件
加地さんは、不当解雇事件を扱った経験が豊富ですか?
2024年2月現在、ざっと調べただけで80件ほどの不当解雇事件を受任してきました。 詳しく調べればもっと増えるかと思います。
名前だけ貸したような事件はありません。全て私が1人であるいは中心となって取り組んだ事件です。
不当解雇事件を1人でこれだけの数経験している弁護士は、それほど多くはいないと思います。
そのうち何件で勝ちましたか?
申し訳ありませんが、勝訴率など具体的な数字は、日本弁護士連合会の取り決めで言えないことになっています。
ただ2024年2月現在、解雇事案で敗訴の判決をもらったことは、ほとんどありません。
単に事件を選んでいるからに過ぎないかもしれないので自慢するつもりはありませんが、1つの事実としてお伝えしておきます。
負けたケースではなぜ負けたんですか?
1つには、裁判官との見解の相違です。
高給で中途採用されたけれど3ヶ月間結果を出せなかった労働者がいたとしましょう。
こうした争いにおいて、裁判官が向こうの主張に理解を示したいうケースがありました。 私は今でも納得がいっていませんが。
事件を受任した段階ではいけそうだと思ったが、後から不利な事実が出てきて負けたというケースもあります。
パワハラが理由で解雇されてしまった労働者のケースですが、私が当初思っていたよりハラスメントの程度が重く、厳しい闘いになりました。
私は事前のヒアリングに力を入れているので、後からの「こんなはずじゃなかった」はほとんどないのですが、 パワハラ事案では往々にして依頼人本人が過去の言動を忘れており、私がヒアリングしきれないことがあります。
これは勝ち目が薄いなぁと感じるのはどんなケースですか?
労働者が犯罪的なことをしている場合がそうです。 横領をしたであるとか同僚の財布からお金を抜き取ったであるとか。
犯罪ではなくとも、勤務態度が悪く、それを改めようとしなかったケースでは、裁判は難しくなります。
勤務中にふらっと煙草を吸いにどこかへ行ってしまうとか、上司に反抗的だとか、私用で休むとか。
注意されてもそうした行為を改めない労働者はいます。 裁判所は、そうしたケースでは、厳しい態度を取ります。
逆に、頑張っているんだけれど能力がいまひとつ足りていない、という労働者には、裁判所は優しめです。
厳しいケースであっても腕の良い弁護士に頼めば勝てるものなんですか?
解雇事案に限らず、誰が見ても厳しいというケースにおいて、弁護士の努力により勝てるとはあまり思えません。 説得すべき相手は素人ではなくプロ中のプロである裁判官ですから、小手先の主張でだますことなどできません。
大事なのは事実関係であり、法的な理屈づけではありません。 事実関係がこちらに断然不利であれば、弁護士にできることは多くありません。
つまり結局のところ裁判は、勝てるケースなら勝てて、負けるケースなら負けるということですか?
はい、勝てるケースでは勝ち、負けるケースでは負けるでしょう。
ただしその中間の、どちらに転ぶかわからないケースがたくさんあります。 そういうケースでは、弁護士の腕の差はかなり出るだろうと思います。
また、同じ勝つにしても、獲得金額に差が出るでしょう。 解雇事案においては、和解で決着したときにそれが顕著だろうと思います。
弁護士の力の差はどういったところに出るんですか?
経験を積んだ良い弁護士ほど、事件の見通しを正確に立てられるでしょう。解決金の相場や相手の出方が読めるので、相手に譲歩しすぎて低い額の解決金で決着することが減るでしょう。
良い弁護士は依頼人へのヒアリングを充分に行います。 弁護士が事実を充分に把握していなければ、言葉が死にます。 死んだ言葉では裁判官の心には響きませんし、相手方の弁護士にも侮られます。
と交渉段階で相手に思わせるのが良い弁護士です。
良い弁護士は自らの主張の弱い部分を見極めることができ、かつ、そこに素早く対処します。 そうでない弁護士は、弱い部分に気づかず、またその点への対処もおろそかになってしまうことでしょう。
弁護士はふつう、同時に数十件の案件を抱えているので、1つの案件に集中してはいられません。そのため後でもできる仕事は後回しにしたい、言わば「明日できることは今日するな」という考えになりやすいものです。しかしその判断を誤り準備が間に合わなくなることもあります。
今すべきことなのか後でもいいのか、という判断を正確にできるのは、良い弁護士です。
良い弁護士は訴訟を恐れないでしょう。そうでない弁護士は、訴訟にかかる手間を嫌がり、早々に低い条件で和解させたがるでしょう。
弁護士にとって、50の労力で150万円の報酬を得るのと、100の労力で200万円の報酬を得るのとだったら、前者の方が効率的かもしれません。
依頼人の利益最大化のために働いてくれるのかは、弁護士の性格次第なところがあります。 訴訟を嫌がり、依頼人に過度の妥協を迫るのは、良い弁護士ではないと思います。
でも、訴訟を恐れる弁護士かそうでないか、どうやって見分ければいいんですか?
その弁護士がヒアリングを充分におこなってくれるかどうかです。 相手方の弁護士と交渉をしていると、
とすぐにわかる弁護士がいます。そういう弁護士は決まって訴訟をしてきませんでした。面倒な訴訟から逃げ、和解を求めてきます。 または、交渉段階では強気でも、こちらが訴訟を起こした途端、和解を提案してきます。
反対に、良い弁護士なら正式に受任する前のヒアリング段階で事件についてあらかた調べてしまっているので、訴訟を起こしても大きく手間は増えません。今まで調べたことや検討したことをただ書面にまとめるだけだからです。
良い弁護士が事件を受任するのはかなりの程度見通しが立っている時であり、その段階ではもう裁判をする覚悟などとうに出来ているのです。
裁判なんかしても大してお金も取れないし疲れるだけだからやめておけ、と周囲から言われます。 加地さんのこれまでの依頼人は満足をしていましたか?
本音ではどうかわかりませんが、そういう声をもらうことが多いですし、実際に満足をして頂けたことが多いのではと感じています。
それはつまり得た金額の面でということですか?
意外に思われるでしょうが、依頼人の満足度を決めるのは裁判の勝ち負けや解決金の額とは限りません。
とはいえ解決金の額についても、私は和解金の世間一般の解決相場は安すぎると感じていて、相応の金額を会社に請求するので、金額的にも満足していただいていることが多いのではないかと思っています。
よくわかりませんが、依頼人にとって、勝ち負けや金額以上に重要なものがあるんですか?
いざ弁護士に依頼をしてみると、依頼人が気にするのは勝ち負けや金額よりも、 弁護士がどれだけ自分のために働いてくれたか、という点なのです。 本当にそういう人が多いです。
裁判にはっきりと負けたケースであっても(もっとも私は裁判でほとんど負けていないのですが)、依頼人から責められたことはありませんし、別の事件でリピーターになってくれたり、知人を紹介してくれたりもしてもらっています。
逆に、他の弁護士に依頼をしている人が、私のところに相談に来たことが何度もあります。
依頼している弁護士に聞けばいいじゃないですかと私は言うのですが、依頼人が言うには、知りたいことを弁護士が教えてくれないとか聞くまで教えてくれないといったことに強い不満を感じているのです。 進捗状況、今後の見通し、証人尋問のスケジュール、どんな準備をしておけばいいのか、などについてです。
いくら裁判に勝ったところで他の弁護士ならもっと勝てたのでは?と思うなら、満足度は低いものになるのです。
じゃあ加地さんは依頼人のことを真剣に考えてくれると言うのですか?
私は依頼人からかなり力を入れてヒアリングを行います。 正式に受任をする前にです。詳細に聞きとります。
それは依頼人のためでもありますが、自分のためでもあります。 「事件をつかめた」と感じる前に事件を受任するのが嫌なのです怖いのです。
自分のためにしていることなので全然苦ではありません。しかし依頼人には、
といった感想を持ってもらえます。 自分のために時間を使うことを惜しまない点を、依頼人は評価してくれるようです。
逆に、あれこれ聞かれることを嫌がったり面倒がる人は、ヒアリング段階で私から離れていきます。 ミスマッチを避けることができて、お互いにとって良いことだと思います。